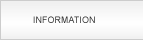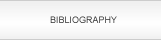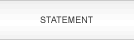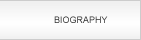藤井健仁作品への試論「新しい対極」
川崎市市民ミュージアム
仲野 泰生
「鉄の宇宙は直接に手の届く世界ではない。そこに近づくためには、火を、硬い物質を、力を愛する必要がある。人はただ、根気よく訓練を重ねた創造的行為を通じてのみその世界を知るのだ」
(『鉄の宇宙』ガストン・バシュラール※1)
高度資本主義の蔓延によって、気がつかないうちに自分の生き方や欲望までがもコントロールされ、細分化されている現代日本の社会。このような社会の中で表現者として生きていくのは、なかなか困難な生き方かもしれない。そんな生き方をあえて行なった日本人の一人に岡本太郎がいる。岡本は戦後、パリでのアーチストとしての生活より「泥のような日本の現実※2」の中で、全人間的に生きることを選んだ。彼はこの日本を生きる方法として「対極主義」を提唱。「対極主義」は、はじめ岡本の絵画制作の中から「シュールレアリスムの技法」の変容として生まれたようだ。例えば「ディペイズマン」や「ダブルイメージ」などの発想は、初期の岡本絵画の謎を紐解く鍵になっている。しかし、最終的に岡本は「対極主義」を「ダイナミズムを起こす装置」として、『太陽の塔』などにみられるように対極の一つを「己の作品・生き方」にし、もう一つの極を「大衆」に定め「大衆と芸術」の対極主義へと、さらに展開していくのだが。
ここで語る藤井健仁も対極を抱えながら制作している作家に見える。藤井が鉄の素材で作る著名人たちの面や少女、そして猫や昆虫たちの世界。彼はどうして、これら作品の創造主となりえたのか。この拙文は、藤井の作品に近づくささやかな試みである。
鉄は(頭の中の知識を辿ると)近代を支えた素材である。武器であり、車であり、ビルの建築材である。現代日本の都市のあらゆる所に、様々な形で変容を繰り返しながら偏在している。また、鉄は古代に発見されながら、木や土や石などの自然の素材とは明らかに異なる変化を遂げた物質だ。ところが藤井の作品に真正面から向き合うとき「鉄の本来の形象とは?」「鉄はどのようなときに真の姿を顕わすのか?」など、幾つかの鉄をめぐる問いが私の頭の中を巡る。
藤井は、自分の中で系統的な制作の流れを幾つかもっている。この意図された制作は旧来の彫刻家の作業というよりも、労働(鍛冶屋)に近い。たとえば、彼の鉄面皮のシリーズ。鉄そのものを藤井の身体による力技で、メディアやわれわれの記憶に浮かび上がった人物たちの顔に変える。現代の仮面の誕生なのか。否、メディアに流布されるこれらの人物たちから意味を剥ぎ落とす為に、藤井は鉄との労働に徹する。以前の個展ではこの鉄の顔たちが、さらし首のように並んで展示された。現代は「前近代的社会において意味を担っていた仮面」が存在し難い時代だ。かつては人間でありながら仮面をつけることで、人間を超え、霊となった。仮面は、安定した共同体を祝祭的に揺さぶり、生の活性化を促す役割として存在していた。しかし、藤井の鉄の仮面はまるで死に向う「供儀」のように見える。仮面とされた三島由紀夫や麻原彰晃等が、「いけにえ」なったのではない。何故なら、鉄と格闘し、制作の中に没入することで生まれたこれらの仮面は、誰彼に似ているという次元を超え(もちろん似ていることが前提になるのだが)、「個」の果ての「個」になっていく。つまり、現代日本に生きる我々誰にでも当てはまるような無意味でありながら深層的でもある「個」に。だから藤井の鉄面皮が多義的な意味で「供儀」に見えるのは、モデルの形象を作りつつ、モデルに貼りついた意味を叩き、素材の鉄の意味さえも消し去ろうとしているからだろう。
ところで藤井健仁は自身の制作の中に、反語的な意味で「近代彫刻史」を内包する作家である。オーギュスト・ロダンを思い起こすまでもなく、人体を制作することで量・面・動勢等の造形言語を発見し、「近代彫刻」は発展してきた。しかし、藤井のもう一つのシリーズ「NEW PERSONFICATION」と名づけられた鉄の人形たちは、「近代」のアンチテーゼとしての存在感を持ちつつある。それは彼が作るのは、あくまでも「人体」でなく「人形」だからであろう。「仮面」や「人形」は、近代彫刻史から巧妙に外された表現ジャンルである。ところが彼の制作した「仮面」や「人形」は、近代の彫刻として育まれた視点や技術の上に成り立っているようにも見える。だから彼自身の制作の中に、反語的な意味も含む「近代彫刻史」が内包されているといったのである。彫刻史を自身の中で内包しつつ、矛盾した位相に転位した彼の「仮面」や「人形」たち。鉄という素材と「人形」というモチーフの対極的な並置を自ら抱えて、藤井は制作しているのではないだろうか。また、藤井の「人形」は、幕末の反近代的産物である「生人形(いきにんぎょう)」に近い存在ではないかと思う。明治以降の近・現代日本の消費社会の中で、鉄による作品を作りつづける藤井の姿は、私にロダンの人体彫刻と対峙する「生人形」の製作者・松本喜三郎※3(1825−1891)を想起させるのである。「生人形」は幕末に見世物興行の細工物の一つとして発展した。この松本のロダンとは異なるすさまじいリアリズムは、幕末の大阪・難波新地や東京・浅草の興行場に集まる大衆の欲望を具現化するものであった。スミソニアン国立自然史博物館・保存研究所の調査によると、松本の「生人形」の素材は木彫を基本としているが、ガラスの眼球のはめ込みや頭髪・陰毛・腋毛は1本ずつ植毛されていることがわかった。皮膚のリアリティは、ジェッソ剤の上から顔料の彩色と漆を併用しているのである。木という伝統的な素材をいじりまわし、極点に達した技法は全て松本自身の手業の所作から生まれている。この技法に類する現代作家とを簡単に比較してみたい。例えば、現代日本を代表する木彫の彫刻家・舟越桂。舟越の作品は木彫を基本とし、ガラスの眼球や彩色をするミックスド・メディアの技法ということでは「生人形」の技法と似ている。しかし、出来上がった作品は、何かが大きく異なるのだ。それは、松本喜三郎の作品は幕末の見世物的な俗世界にありながらも、松本の作品は「近代性」をすでに獲得していたのではないかという点。それに対して舟越の作品は近代主義の文脈の中で、優れたセンスにより生まれた作品である。その意味で二つの作品世界は、見た目は似ているが、その内実は全く異なっている。
さて、今回の藤井の出品作品にも、舟越作品に近似した形でトリミングした胸像の少女像がある。藤井の作品は、全身像で作られることが多いが、新作『海から離れて(bust)』は上半身の作品。舟越の作品は木に彩色を施し、人間の皮膚に近づこうとする表現に見える。反対に藤井の鉄の少女は、鉄の皮膚を持ちつつ人間の少女像とは距離を保っている。つまり少女・人形というモチーフのイメージに追従せず、鉄の素材が内在する獰猛な暴力性までも同時に保持しているのである。また、彼の作る少女の顔は、異形の面立ちであり、先の鉄面皮シリーズの表情とも異なる。この異形の面は、藤井の妄想の産物というよりも、オセアニアやメキシコの仮面を連想させる。アミニズムに彩られた集合的無意識の形象である仮面に、彼の人形の顔が近づいてみえるのは何故か。
それは、アンドレ・ブルトンがメキシコを訪れたとき「ここはすでにシュルレアリスムに溢れている※4」と発言した位相と、彼の鉄人形の世界が通底しているからかもしれない。つまり藤井の作品は、鉄を徹底的に弄繰り回した結果、鉄でありながら鉄でない鉄の新たな極点を垣間見せ、イメージに拠らないもう一つのディペイズマンを可能にしているのではないだろうか。彼の作品は、舟越の木彫があくまでも木という素材の調和の中にあるのとは対極の世界なのである。また、松本喜三郎の「生人形」が、日本が近代主義に追従する前に、優れた「近代性」を内包し凌駕した作品だったのと同様に、藤井健仁の「鉄の人形」も鉄という近代の象徴的な素材を使いながら、鉄の「近代」の意味・位相とはまったく異なる次元の鉄自身の顔・表情を見せたのである。そして、鉄面皮と鉄人形の二つの極点を持ちつつ制作する藤井の姿勢こそ、新たな物質のディペイズマンであり、新しい対極主義の可能性を私たちに見せてくれるのだ。
2007.2.19
註
※1ガストン・バシュラール『夢みる権利』1977年渋沢孝輔訳
筑摩書房刊行
※2『別冊 アトリエ 岡本太郎特集号』1955年
アトリエ刊行
※3『生人形と松本喜三郎』2004年
熊本市現代美術館 図録
※4アンドレ・ブルトン『魔術的芸術』1997年巌谷國士監修訳
河出書房新社刊行