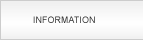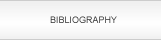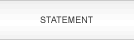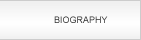いま私たちは鉄の声を聞くことで三島や麻原を超える
〜藤井健仁「彫刻刑 鉄面皮」展覧会に寄せて〜
宮台真司
【モダンアートとは何か?】
いま私の手元に二つの「鉄面皮」がある。麻原彰晃と三島由紀夫。私が所望した。二人とも「内在」ならぬ「超越」を志向した。人々を「超越」へと向けて方向づけようとした。「内在」とは〈世界〉の中にあること。「超越」は〈世界〉を超えていること。
内在と超越の二項図式は神学の概念だが、〈社会〉の中にあることを「内在」と呼び、〈社会〉の外の〈世界〉に触れていることを「超越」と呼ぶ用法もある。両方とも、暗黙化された全体性を境界づけ、超えようとする志向に関係する。
〈世界〉とはあらゆるものの全体。〈社会〉とはコミュニケーション可能なものの全体。古い社会では両方は重なる。私たちの社会ではコミュニケーション可能なのはヒトに限られ、〈社会〉の外にコミュニケーション不能なものからなる〈世界〉が拡がる。
芸術とは何か。極北はモダンアートだ。アンディ・ウォホールのキャンベルスープを見よ。これらは美術館に展示されるからこそアートになる。つまりアートは文脈に依存してアートになる。存在するべき場所(美術館)にあるからアートになる。
音楽の存在が期待されるコンサートホールという場所だからこそ、そこでは音楽の不在がアートになる。ジョン・ケージの「4分33秒」だ。これを「アートの制度性」と言う。二〇世紀のアートはこの制度性を自覚した上、あえて逆手に取ろうとした。
分かりやすい例が「音」と「音風景」の差異。ないし「音楽」と「音楽のある風景」の差異。音楽を自体的に享受するより、場違いを含め、ある場所で音楽が流れているという事態を享受する。校庭で各所から聞こえるバンド練習の音の混じり合いを楽しむように。
これは直ちに批評に繋がる。難しいことではない。音風景を享受する態度をとるや否や、音と雑音の区別や、音楽と非音楽の区別の自明性が崩れ、全て等価となる。同じく然るべき場所と然るべからざる場所の区別の自明性も崩れ、全て横並びとなる。
その結果〈社会〉の自明性が崩れる。コミュニケーションが分節する自明性が崩れる。「ヒトのなす区別」の当たり前さが崩れる。〈社会〉の外の「端的なもの」が出現する。「そういう〈社会〉がある」という、〈社会〉に回収できない「端的な事実」が露呈する。
そのことを通じて、私たちは〈社会〉に閉じ込められていたことに気付く。それまで自分が解放されたと思っていても、ソレを解放と呼ぶ〈社会〉に閉じ込められていたことに気付く。「ヒトのなす区別」の内側に閉じ込められていたことに気付く。
もちろん私たちは「ヒトのなす区別」の外側に出られない。従って〈世界〉の全体性を手中に収めることは論理的にあり得ない。だが、私たちは普段そのことを意識せずに生きる。しかしヒトにはそれを意識したくなるときがある。何もかもウンザリだからだ!
【鉄人形は「モダンアートな体験」を超える】
人形(にんぎょう、または、ひとがた)は、ヒトであってヒトでないという両義的な性格ゆえに、古来、〈社会〉の「弱い場所」、ないし、〈世界〉へと開いた窓として受け止められてきた。つまり、人形は〈社会〉に置かれるには危険な物体なのだ。
人形は〈社会〉に「闇の力」を引き込むものだと考えられてきた。〈社会〉すなわち人間関係から来る「横の力」には還元できない〈世界〉から来る「縦の力」を呼び込むものだとされてきた。アートと異なり、人形はどこに置かれていても「力」を発揮しうる。
人形の「力」を偏愛する私は、小さい頃から数々の人形劇を見続けてきた。大人になってからは文楽や糸操人形(結城座)の浄瑠璃を見続けている。天野可淡や山吉由利子の人形展があれば出かける。フィギュアのワンダー・フェスティバルにも出かける。
藤井健仁氏の1999年の作品「海から離れて」(日向あき子賞)を一目見た私は、この鉄人形の「力」に感動した。以降この鉄人形は私のベッドの横に立ち、いつも私のことを見下ろしている。
この鉄人形が与えてくれるものは、私の人形体験の中でも特異だ。それは、素材があからさまに鉄であること、どうみても鋳物には見えないことに関係する。この人形は、「人形についての体験」と「鉄についての体験」とを二重に与えてくれるのだ。
「人形についての体験」は先に述べたように場所に依存しない。ところが「鉄についての体験」はモロに場所に依存する。私たちは普通の生活で、鉄がこうした形で存在するのを目撃することはあり得ないからだ。その経験は文字通り「シュールレアル」だ。
私たちの知る鉄は、鉄橋や鉄塔であり、ビルの鉄筋や鉄骨であり、自動車や船舶の素材だ。そのようにある限り、鉄は私たちが慣れ親しんだ〈社会〉に舞台装置として溶け込む。私の寝室にある鉄人形は、「場違いな鉄」だから、〈社会〉に溶け込まない。
その結果、〈社会〉すなわち「ヒトのなす区別」の当たり前さが崩れる。私たちが「そういう〈社会〉を当たり前だと思っている」という、〈社会〉に回収できない「端的な事実」が露呈する。いわば「モダンアートな体験」が生じる。
ただし通常ならそこで「私たちが」自明性の檻に閉じ込められていたことが明らかになって終わる。ところが「場違いな鉄」が鉄人形という形をとることで、鉄自身が「閉じ込められていたのはお前らヒトじゃなく、俺たち鉄だ」と主張し始める!
【史上初めて「鉄の声」を聞く私たち】
いま、私の目の前にある三島由紀夫と麻原彰晃。二人とも「超越」を志向した。〈社会〉ではなく〈世界〉を志向した。言い換えれば、「ヒトのなす区別」の向こう側を志向した。その二人が、いま「鉄面皮」という形をとって、私の目の前に存在する。なぜか。
私をいろいろな妄想が襲う。二人ともヒトが「ヒトのなす区別」のこちら側に閉じ込められてあることに苛立った。私もいつも苛立っている。二人はいわば、私のような者どもの声を聞いてはいる。だが、二人は、鉄の声には耳を傾けただろうか。
冒頭に述べたように、かつてはどこでも〈世界〉は〈社会〉だった。ありとあらゆる全体がコミュニケーション可能だった。部族段階におけるアニミズムやトーテミズムのことだ。私たちはヒトの声を聞くように、木の声、水の声、石の声、「鉄の声」を聞いた。
いや、違う。歴史の教えるところによれば、どの部族社会も、「スキタイの鉄」を手にするや、ほどなく部族段階を脱してしまい、木の声、水の声、石の声を聞かなくなる。先人たちは世界中どこでも、「鉄の声」に限って、これを聞いたかどうかが微妙なのだ。
私(たち)がこれらの「鉄面皮」を通じて、あるいは私の寝室にある「海から離れて」を通じて、「鉄の声」を聞くのだとすれば、だから人類史上初めてのことだ。私(たち)は史上初めて、鉄が鉄の望む場所にあるのかどうかについての「鉄の声」を聞くのだ。
三島や麻原といえども、鉄が声を発していることに気付かなかっただろう。結局彼らも「ヒトのなす区別」の自明性によって耳を塞がれていたということだ。とすれば、いまここで鉄の声に耳を傾けている私は、彼らよりも自由だ──などなど妄想は拡がる。
こうした妄想系列に従えば、いま私たちに声を届けようとしている鉄が、三島由紀夫、麻原彰晃、金正日、浜崎あゆみ…といったカリスマの人形(ひとがた)をとることは、大いなるアイロニーと言うほかない。私(たち)はそこに「鉄からの嫌がらせ」を聞く。
近代社会学の父マックス・ウェーバーに従えば、カリスマとはすなわち、金力や武力などの属性(=横の力)には還元しえぬ非日常的資質(=縦の力)だ。しかるにカリスマを帯びるとされる先の者どもは、真に「横の力」から自由か? 鉄がそう問うてくる。
「ヒトのなす区別」によってヒトに加えられた恣意性の暴力にのみ敏感で、「ヒトのなす区別」によって鉄に加えられた恣意性の暴力に鈍感な者どもが、「自らはカリスマを帯びたる者なり」と自称するのか? これは滑稽千万。不遜極まりないではないか。
そういうわけで、このたび鉄は、鉄の声を聞かずしてカリスマを自称した者たちを「鉄面皮の刑」に処するに至った。当然だ。それが、三島由紀夫と麻原彰晃が「鉄面皮」とはいう形をとって私の目の前に存在するということの意味なのだ。
元々「根が眩暈系」の私は、小さい頃からヒトではない様々なモノが発する声に耳を傾けてきた。人呼んで「空耳野郎」だった(笑)。たぶん鉄は、そんな私をこそ仲間だと思ってくれるのではないか──などと妄想が尽きない。私は変かもしれない。